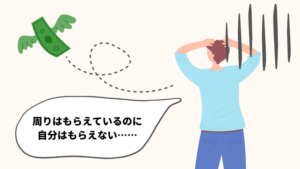「趣味で始めたブログだったのに、収益化を目指した途端に書くのが苦痛になってしまった」
「良かれと思って部下にインセンティブ(報酬)を出したら、かえって事務的な対応になってしまった」
こんな経験はありませんか?
本来「楽しいから」「好きだから」と自発的に行っていた行動に対して、金銭などの報酬を与えると、逆にやる気(モチベーション)が下がってしまうことがあります。
この心理現象を「アンダーマイニング効果(過正当化効果)」と呼びます。
今回は、なぜご褒美が逆効果になるのか、そのメカニズムと、やる気を削がずに相手を称賛するための具体的な対策を解説します。
アンダー・マイニング効果の概要
アンダー・マイニング効果とは、報酬が与えられることによって、本来楽しいと感じていた活動がつまらなく感じられるようになる現象のことです。
この効果は、内発的動機づけ(内的動機づけ)が外発的動機づけ(外的動機づけ)によって阻害されることによって引き起こされます。
- 内発的動機づけ: 「楽しい」「面白い」「やりがいがある」といった、自分の内側から湧き出るやる気。
- 外発的動機づけ: 「給料がもらえる」「怒られないため」「評価されるため」といった、外からの刺激によるやる気。
内発的動機づけと外発的動機づけについては、下記の記事もご参照ください。

原因は「自己決定感」の喪失
なぜ報酬をもらうとやる気が下がるのでしょうか?
それは、行動の理由が「自分がやりたいから(自己決定)」から、「報酬をもらうため(他律的)」へとすり替わってしまうからです。
人は「自分の行動は自分で決めている」という感覚(自己決定感)を強く求めます。
しかし、報酬が目的になると、「報酬のためにやらされている」と感じてしまい、自己決定感が失われ、結果として純粋な興味や意欲が失われてしまうのです。
身近な事例で見るアンダーマイニング効果
【実験】絵を描くのが好きな子供たち
心理学者マーク・レッパーらが行った有名な実験があります。
絵を描くのが大好きな園児たちを3つのグループに分けました。
- 予期された報酬グループ: 「絵を描いてくれたらご褒美をあげるよ」と約束してから描かせる。
- 予期しない報酬グループ: 何も約束せずに描かせ、終わった後にサプライズでご褒美をあげる。
- 報酬なしグループ: ご褒美なしで描かせる。
数日後、自由時間に誰が絵を描くか観察したところ、「1. 予期された報酬グループ」の子供たちだけが、絵を描く時間が劇的に減ってしまいました。
彼らにとって絵を描くことは、「楽しい遊び」から「報酬をもらうための労働」に変わってしまったのです。
【ビジネス】「メンター手当」の落とし穴
ある会社で、ベテラン社員Aさんが自発的に若手の相談に乗っていました。
会社はそれを評価し、「メンター手当」として報酬を出すことにしました。
するとどうなったでしょう?
Aさんは次第に、「手当の分だけやればいい」「これは業務だ」と感じるようになり、以前のような親身な相談をしなくなってしまいました。
「若手の力になりたい」という内発的動機が、「手当をもらう業務」という外発的動機に上書きされてしまったのです。
なぜ起きる?効果が発生しやすい3つの条件
すべての報酬がやる気を下げるわけではありません。アンダーマイニング効果は、特に以下の条件が揃った時に発生しやすくなります。
- 「予告された」報酬(If-Then型): 「もし〇〇したら、報酬をあげる」という条件付きの提示。「報酬のためにやる」という意識を強く植え付けます。
- 「形のある」報酬: 金銭、物品、表彰状など、目に見える外的な報酬。
- 「監視・評価」を伴う環境: 報酬のために監視されている、評価されていると感じる状況。
対策:やる気を維持するマネジメント術
では、相手のやる気を削がずに報いるにはどうすればよいのでしょうか?
「言語的報酬(称賛)」を活用する
金銭とは異なり、「言葉による称賛(ポジティブフィードバック)」は、アンダーマイニング効果を起こしにくいと言われています。
「君のおかげで助かったよ」「素晴らしい仕事だね」という言葉は、相手の有能感を高め、「自分の仕事には価値がある」という内発的動機を強化します。
「予期せぬ報酬」として渡す
レッパーの実験でも示された通り、事前の約束なしに、終わった後に「素晴らしい成果だったから」とサプライズで渡す報酬は、やる気を下げにくいです。
これは「報酬のためにやった」という認識になりにくく、「自分の成果が認められた証」として受け取られるからです。
自律性を尊重する
「あれをやれ、これをやれ」と細かく指示して報酬で釣るのではなく、やり方や進め方を本人に任せましょう。
「自分で決めてやった」という感覚(自律性)が守られていれば、報酬があっても内発的動機は維持されやすくなります。
まとめ
報酬は、使い方を間違えると「やる気の特効薬」どころか「毒」にもなり得ます。
特に、相手がもともと楽しんでやっていることや、クリエイティブな仕事に対しては、安易な金銭的報酬は逆効果になるリスクがあります。
大切なのは、相手の「自己決定感」を奪わないこと。
「お金」でコントロールするのではなく、「言葉」で感謝を伝え、相手の自律性を尊重することが、長期的なモチベーションを育てる鍵となります。
報酬のデメリットについては、下記の記事もご参照ください。