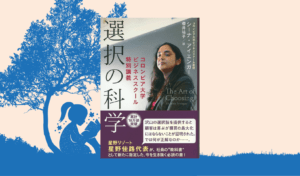仕事をしていると、「今日はどうしてもやる気が出ない」「もっと頑張りたいのに体が動かない」という日があるものです。 そんな時、気合や根性で乗り切ろうとする前に、まずは「人の心はどういう時に動くのか?」という仕組み(理論)を知っておくことが大切です。
ここでは、ビジネスの現場でよく使われる4つの基礎理論を紹介します。自分の今の状態がどれに当てはまるか、チェックしてみてください。
欲求の5段階説(アブラハム・マズロー)
「人間は、低い次元の欲求が満たされて初めて、より高い次元の欲求を求める」という有名な理論です。
例えば、職場の人間関係が悪くて不安な状態(社会的欲求や安全の欲求が満たされていない状態)では、「自己成長したい!(自己実現の欲求)」という高いモチベーションを持つことは難しいとされています。
今の自分がどの段階にいるのかを知るための羅針盤となる理論です。
このマズローの5段階欲求については、下記の記事をご参照ください。
X理論・Y理論(ダグラス・マグレガー)
人間に対する2つの対照的な見方を示した理論です。
- X理論: 「人間は本来怠け者で、強制されないと働かない」という見方(アメとムチによる管理)
- Y理論: 「人間は条件次第で、自ら進んで責任を取り、目標に向かって努力する」という見方
もしあなたが上司から細かく管理されすぎてやる気を失っているなら、それは「X理論」で扱われているからかもしれません。逆に、もっと裁量権を持って働きたいと感じるなら、あなたは「Y理論」的な働き方を求めていると言えます。
X理論・Y理論については、下記の記事もご参照ください。
動因と誘因(内発的動機づけ vs 外発的動機づけ)
やる気の「源泉」がどこにあるかという話です。
- 動因(内発的): 「仕事そのものが楽しい」「好奇心が満たされる」といった、自分の内側から湧き出るやる気。
- 誘因(外発的): 「給料がもらえる」「怒られないようにする」といった、外からの刺激によるやる気。
どちらも大切ですが、長く安定して働き続けるためには、自分なりの「動因(内なる楽しさ)」を見つけることが重要になってきます。
この動因と誘因の違いについては、下記の記事もご参照ください。
「選択」の力
「やらされている仕事」と「自分で選んだ仕事」。たとえ作業内容が同じでも、モチベーションには天と地ほどの差が生まれます。
人は「自分で選択した」という感覚(自己決定感)を持つことで、パフォーマンスが向上し、人生の満足度も高まることが研究で分かっています。
日々の小さな業務の中に「自分で選ぶ」要素を取り入れることが、やる気のスイッチになります。
この選択の力については、下記の記事もご参照ください。