集団思考とは
集団思考(Groupthink)とは、心理学者アーヴィング・ジャニス(Irving Lester Janis)が定義した言葉で、グループが不適切または不合理な決定を下すプロセスを表しています。
「会議の雰囲気を壊したくないから、反対意見を出さない」「優秀な参加者が多いから、彼らに任せて自分はアイデアを出さない」という考えは、集団思考の最たる例です。
グループで話し合ったにもかかわらず、グループで考えたメリットを享受できず、生産的なアイデアを出せなかったり、個人で考えた時よりも不合理な決定を下したりする状況が集団思考です。
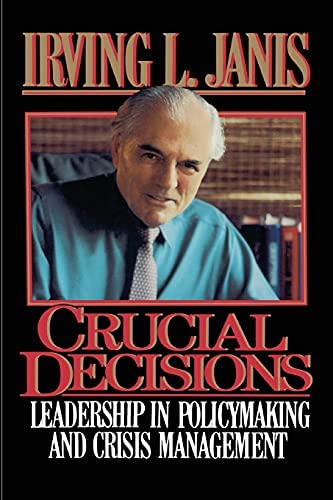
集団思考については、動画でも解説しています。よろしければご覧ください。
集団思考の原因
集団思考が発生してしまう原因は様々ですが、代表的なものは以下のとおりです[1]What Is Groupthink?(2022年11月2日閲覧)を参考に作成。。
- グループの高い凝集性
- リーダーの影響
- 乏しい知識
- ストレス
ここからは、集団思考の各原因について解説していきます。
グループの高い凝集性
グループの凝集性が高い場合は集団思考につながる可能性があります。
凝集性が高いグループとは、似たような考えの人で集まっているグループのことです。
凝集性の高いグループでは、出てきた意見に対して反論が出にくくなります。また、反論を持っていたとしても、グループでの意見を尊重して、発言しないということもあります。
その結果集団思考が働き、集団で考えたアイデアにもかかわらず、効果的ではないという状況が生まれます。
またグループの凝集性が高いと、「自分たちのグループが正しい」と言う思想にも囚われがちになり、批判的な意見を受け入れず、集団思考に陥ります。
リーダーの影響
集団思考にはリーダーの存在も影響しています。
リーダーの影響が強すぎる場合、たとえばリーダーの発言を是とする雰囲気がある場合は、その意見への反論がしにくくなり、集団思考が発生します。
一方、リーダーの影響が弱すぎる場合でも、公平な議論の場が作られず、特定の人物の意見ばかりが尊重されるという状況になってしまいます。
乏しい知識
乏しい知識も集団思考の原因になります。
冒頭で例として出した「優秀な参加者が多いから、彼らに任せて自分はアイデアを出さない」という状況は、参加者の知識不足から生まれます。
また、知識が低いと、知識の高い人の意見に盲目的となる傾向があるため、これも集団思考につながってしまいます。
ストレス
参加者のストレスも集団思考の原因の1つです。
外部からの圧力や所属している組織のジレンマなどで、自由な意見交換が阻害されてしまうと、それが集団思考につながってしまいます。
集団思考の解消法
ここからは集団思考の解消法を紹介していきます。
批判や反論を奨励する
批判や反論を奨励し、受け入れることは集団思考解消に役立ちます。
批判意見が出にくい場合は、批判意見だけを言う役割を設け、批判意見を促しても良いでしょう。
適切なリーダーシップ
適切なリーダーシップは、集団思考の解消を助けます。
グループでの話し合いで、公平に参加者から話を聞き、反対意見を歓迎する雰囲気づくりを、リーダーは心がけなければなりません。
また、リーダーとして自身の意見を言ってしまうと、他の参加者がそれに同調する可能性もあるので、自身の意見を前面に出さないようにすることも大切です。
集団思考とパーキンソンの法則との違い
集団思考に似た意味を持つ言葉に「パーキンソンの法則」と言うものがあります。パーキンソンの法則はイギリスの歴史学者・政治学者シリル・ノースコート・パーキンソン(Cyril Northcote Parkinson)が1957年に発表した「組織は些細なものごとに対して、不釣り合いなほど重点を置く」という主張のことです。
このほかにもパーキンソンの法則には「仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する(第1法則)」、「支出の額は、収入の額に達するまで膨張する(第2法則)」という主張も含まれており、集団であるが故に機能不全を起こしている組織の失敗が指摘されています。
集団思考はこのパーキンソンの法則を発展させたという面もあります[2]Groupthink – Wikiwand(2022年11月2日閲覧)。
パーキンソンの法則が非生産的な組織になっていくメカニズムに注目したのに対し、集団思考は集団が非生産的・非合理的なアウトプットをするメカニズムに注目しています。
パーキンソンの法則については、下記の記事もご参照ください。
参考
- ロルフ・ドベリ(著)、中村智子(訳)『なぜ、間違えたのか? 』サンマーク出版、2013年
注
| ↑1 | What Is Groupthink?(2022年11月2日閲覧)を参考に作成。 |
|---|---|
| ↑2 | Groupthink – Wikiwand(2022年11月2日閲覧) |


