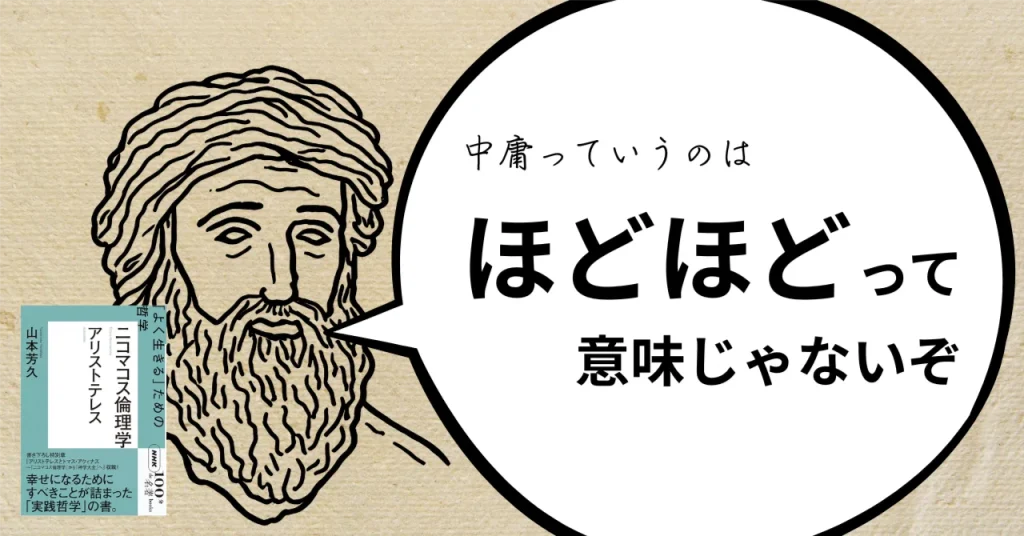【応用情報・診断士 対策】「移動平均法」と「指数平滑法」とは?需要予測のキホンを解説
「来月、この商品はいくつ売れるだろうか?」
経営において、未来の需要を予測することは非常に重要です。
応用情報技術者試験では、過去の売上データ(=時系列データ)だけを使って、将来を予測する時系列モデルについて問われます。
今回は、その代表的な2つの手法、「移動平均法」と「指数平滑法」について、過去問を題材に解説します。
【過去問】(令和7年春期 問74より)
様々な需要予測モデルのもととなっている時系列モデルに関する記述として,適切なものはどれか。ア 移動平均法では,平均する期間を長くするほど,短期的な需要の変化の影響が大きくなる。
イ 移動平均法は,長期的な需要のトレンドを把握するのには向かないが,直近の需要の変化を把握するのには向いている。
ウ 指数平滑法では,平滑化定数の値が0%に近いほど直前の実績値を重視し,100%に近いほど過去の実績値を重視する。
エ 指数平滑法は,過去の実績値よりも直近の実績値を用いるほど予測の精度が向上すると考えられる場合に有効な手法である。
移動平均法 (Moving Average Method)
これは、「過去の一定期間の平均値」を計算して、次の需要を予測するシンプルな手法です。
例えば、「過去3ヶ月」の売上の平均値で、来月の売上を予測します。
5月の売上を予測するなら、「2月、3月、4月」の平均を使います。
6月の売上を予測するなら、1ヶ月ずらして「3月、4月、5月」の平均を使います。(だから「移動」平均と呼ばれます)
特徴(期間の長さ)
- 平均する期間を「短く」する(例:過去3ヶ月)
- 直近の変化に敏感に反応できます。
- しかし、たまたま起きた「短期的な変動(ノイズ)」にも大きく影響されてしまいます。
- 平均する期間を「長く」する(例:過去12ヶ月)
- 短期的な変動(ノイズ)は無視され、なだらかな予測(=長期的なトレンド)が把握できます。
- しかし、直近の急激な変化には鈍感になります。
【具体例】移動平均法を計算してみる
「移動平均法」のイメージを掴むために、ある商品の売上データ(架空)で計算してみましょう。
- 1月: 100個
- 2月: 110個
- 3月: 120個
- 4月: 130個
- 5月: 140個
このデータを使って、「6月」の売上を2つの異なる期間で予測してみます。
A. 期間を「短く」設定(直近2ヶ月平均)
- 計算式: (4月の実績 + 5月の実績) ÷ 2
- 予測: (130 + 140) ÷ 2 = 135個
- → 直近の「130個」「140個」という売上の勢いを強く反映した予測になります。
B. 期間を「長く」設定(直近5ヶ月平均)
- 計算式: (1月 + 2月 + 3月 + 4月 + 5月) ÷ 5
- 予測: (100 + 110 + 120 + 130 + 140) ÷ 5 = 120個
- → 1月の「100個」といった古いデータにも影響されるため、予測値はなだらか(平均的)になります。
このように、期間の設定次第で予測値が大きく変わることがわかります。
【過去問ア・イの解説】
移動平均法の理解が深まったところで、応用情報技術者試験の問題文を読んでいきましょう。
ア 移動平均法では,平均する期間を長くするほど,短期的な需要の変化の影響が大きくなる。
この選択肢は誤りです。期間を長くすると、短期的な影響は小さくなります(なだらかになる)。
イ 移動平均法は,長期的な需要のトレンドを把握するのには向かないが,直近の需要の変化を把握するのには向いている。
この選択肢も誤りです。むしろ逆のことを言っており、移動平均法は期間を長く取れば、長期的なトレンドを把握するのに向いています。直近の変化を把握したいなら、期間を短くする必要があります。
指数平滑法 (Exponential Smoothing Method)
移動平均法は、「3ヶ月前」のデータも「1ヶ月前」のデータも、同じ重みで「平均」してしまいます。
しかし、普通に考えれば「3ヶ月前の売上」よりも「昨日の売上」のほうが、明日の予測には重要ですよね。
そこで、「直近のデータほど重視する(重みを大きくする)」ように、賢く平均を計算するのが指数平滑法です。
次の予測値 = α × 今回の実績値 + (1 - α) × 今回の予測値
- α (アルファ): 平滑化定数(0〜1の値)と呼ばれ、どれだけ「直近の実績」を重視するかを決める「重み」です。
特徴(平滑化定数 α)
- α を「1 (100%)」に近づける
- 「
α×今回の実績値」の重みが最大になります。 - 直近の実績値をほぼそのまま次の予測に使うことになります。
- 「
- α を「0 (0%)」に近づける
- 「(
1 - α) ×今回の予測値」の重みが最大になります。 - 直近の実績はほとんど無視し、今まで予測してきた値(=過去の平均的な実績)を使い続けることになります。
- 「(
【具体例】指数平滑法を計算してみる
「指数平滑法」が「直近を重視する」とはどういうことか、具体的に計算してみましょう。
- 「5月」の売上を予測したところ、予測値は「100個」だった。
- しかし、実際にはブームが来て、実績値は「150個」だった。(予測より50個も多く売れた)
この「予測と実績のズレ」を踏まえて、「6月」の売上を2つの異なる平滑化定数(α)で予測してみます(計算式: 次の予測値 = α × 今回の実績値 + ( 1 - α ) × 今回の予測値)。
A. αを「高く」設定(α = 0.8):直近のブームを重視
- 計算式: 0.8 × (5月実績: 150) + (1 – 0.8) × (5月予測: 100)
- 予測: (0.8 × 150) + (0.2 × 100) = 120 + 20 = 140個
- → 5月の予測(100個)から、5月の実績(150個)に大きく引きずられ、予測が140個へと急上昇しました。
B. αを「低く」設定(α = 0.1):過去の平均を重視
- 計算式: 0.1 × (5月実績: 150) + (1 – 0.1) × (5月予測: 100)
- 予測: (0.1 × 150) + (0.9 × 100) = 15 + 90 = 105個
- → 5月に150個売れたという実績はあまり重視せず、これまでの予測(100個)を信じた結果、予測は105個にしか上がりませんでした。
このように、αの値を調整することで、「直近のデータをどれだけ信じるか」を変えることができるのが指数平滑法の特徴です。
【過去問ウ・エの解説】
指数平滑法の理解が深まったところで、残りの選択肢を確認していきましょう。
ウ 指数平滑法では,平滑化定数の値が0%に近いほど直前の実績値を重視し,100%に近いほど過去の実績値を重視する。
この選択肢は誤りです。完全に逆のことを言っており、指数平滑法では、100%に近いほど直前の実績を重視し、0%に近いほど過去の実績(これまでの予測値)を重視します。
エ 指数平滑法は,過去の実績値よりも直近の実績値を用いるほど予測の精度が向上すると考えられる場合に有効な手法である。
これがまさに指数平滑法の根本的な考え方です。「未来は、遠い過去よりも、直近の過去に影響されるだろう」という思想に基づいています。
まとめ
| 手法 | 考え方 | 特徴 |
|---|---|---|
| 移動平均法 | 過去の平均値で予測 | 期間が長い → 長期トレンド向き(なだらか) 期間が短い → 短期変動に敏感 |
| 指数平滑法 | 直近を重視して平均 | αが高い(100%) → 直近の実績を重視(敏感) αが低い(0%) → 過去の平均を重視(なだらか) |
したがって、適切な記述は エ となります。