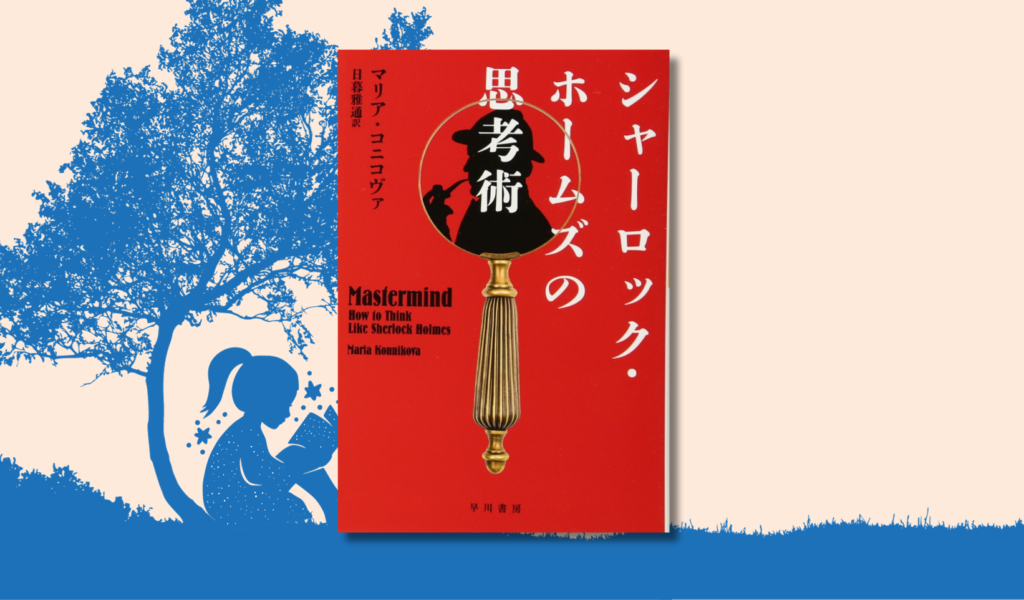用語– category –
-

根本的な帰属の誤りとは何か?ビル・ゲイツの話を例にして解説
根本的な帰属の誤りの概要 根本的な帰属の誤り(Fundamental attribution error)とは、人が他人の行動を判断する際に、個人の特徴を過度に強調し、状況要因を無視するという認知バイアスの一つで「基本的帰属錯誤」「基本的な帰属の錯誤」「基本的な帰属... -

短慮のワトスン・システムと熟慮のホームズ・システム ~要約『シャーロック・ホームズの思考術』その2~
なぜワトスンは間違い、ホームズは真相にたどり着けるのか? 世界一有名な探偵シャーロック・ホームズは、観察と仮説推論による推理によって、難事件を解決していきます。「観察」と「仮説推論」だけであれば、誰でもホームズになれるような気がします。し... -

ハード・イージー効果とは何か?自信過剰の原因となる認知バイアス
ハード・イージー効果の概要 ハード・イージー効果(hard–easy effect)とは、難しいと思われるタスクの成功確率を過大評価し、簡単だと思われるタスクの成功確率を過小評価する傾向として現れる認知バイアスです。ハード・イージー効果は、たとえば個人が... -

不在情報の無視(オミッション・ネグレクト)とは何か?具体例を含めて解説
不在情報の無視(オミッション・ネグレクト)の概要 不在情報の無視(オミッション・ネグレクト, Omission neglect)とは言及されていない、または未知のオプション、代替案、特徴、特性、可能性、イベントなど、あらゆる種類の欠落情報に対して人が鈍感で... -

デフォルト効果とは何か?身近な事例も含めて解説
デフォルト効果の概要 「デフォルト効果」(Default Effect)は、人が意思決定をする際に、特定の選択肢がデフォルト(デフォルト設定)として与えられている場合に、その選択肢を選びやすい傾向がある現象を指します。 この現象は、行動経済学や心理学の... -

ファクトフルネスとは何か?世界を正しく見るために解消すべき10個の思い込みを解説
ファクトフルネスとは スウェーデンの医師で公衆衛生学者のハンス・ロスリングが「事実に基づいた世界の見方をすること」を指して「ファクトフルネス」と名付けました。このファクトフルネスは、客観的なデータと事実に基づいた情報を用いて、物事を理解す... -

ルクレティウス過小評価とは何か?個人的な体験による認知バイアス
ルクレティウス過小評価の概要 ルクレティウス過小評価とは、ある人の個人的な過去の体験が、その人が可能だと考えることを左右しているという認知バイアスです。この言葉は『ブラック・スワン』などの著者として知られるナシム・ニコラス・タレブによって... -

ホットハンドの誤謬(ホットハンド現象)とは何か?
ホットハンドの誤謬とは 「ホットハンドの誤謬(Hot Hand Fallacy)」あるいは「ホットハンド現象(Hot Hand Phenomenon)」は、統計学と心理学の文脈で使われる用語で、成功や失敗などのイベントが連続して起こる傾向があるかのように感じられる誤解を指... -

記憶のための動機付け(MTR)とは何か?スクーター・リビー効果もあわせて解説
記憶のための動機付け(MTR)の概要 「記憶のための動機付け(the motivation to remember)」とは、個人が情報を覚える動機や理由を指し、MTRと略されます。 人は物事を記憶する時、「記憶したい」という動機を持っていた情報を強く残します。一方で、後... -

通俗心理学(ポピュラー心理学)とは何か?
通俗心理学(ポピュラー心理学)とは、大学で研究されているようなアカデミックな心理学が単純化・誇張されたり、あるいはアカデミックな心理学ではほとんど支持者がいないにもかかわらず、その面白さからメディアで流通したりしているものを指します((植... -

利用可能性バイアス(availability bias)とは何か?判断を誤らせる認知バイアスを解説
利用可能性バイアスの概要 利用可能性バイアス(availability bias)は、認知心理学や行動経済学の分野で研究される心理学的なバイアスの一つです。このバイアスは、人々が判断や意思決定をする際に、手元に容易に思い浮かぶ情報や出来事を過大評価し、そ... -

アンカリング効果とは何か?「コーヒー1杯の料金」に騙されてしまう人間の心理について解説
アンカリング効果の概要 アンカリング効果(Anchoring Effect)は、認知心理学や行動経済学などの領域で研究されている心理現象の一つです。アンカリング効果は、人々が意思決定をする際に、最初に提示された情報や価値に影響を受け、その後の意思決定にお...