用語– category –
-

ヒューリスティックとは何か?代表的なヒューリスティックの種類とメリット・デメリットを解説
ヒューリスティックとは ヒューリスティックとは、問題解決や意思決定において、短時間で結論を導き出すための簡易的な方法や思考法のことを指します。言い換えると、複雑な問題に対して直感的に答えを出す方法です。 人は問題に直面した時や何かを決めな... -

認知バイアスとは何か?発生の原因と種類、付き合い方を解説
認知バイアスとは何か? 認知バイアスとは心理学において無意識に発生する「思考の偏り」のことです。簡単に言うと、思い込みや経験によって、ものごとを正しく判断できなくなる心の働きのことです。 例えば、一度悪い印象を持った人に対しては、その人の... -

選択のパラドックスとは何か?~シーナ・アイエンガー『選択の科学』より~
選択のパラドックスとは 選択のパラドックスとは、選択肢の数や特性によって、選択結果が逆転する現象のことを指します。選択肢が多いことは、喜ばしいことです。しかし、選択肢が多すぎれば選択が難しくなり、結果的に満足度は下がってしまいます。たとえ... -

アンコンシャス・バイアスとは何か?原因と弊害、その対処法を事例を交えて解説
アンコンシャス・バイアスとは? アンコンシャス・バイアス(unconscious bias)とは、それぞれの人が無意識に持っている決めつけや思い込みのことを指します。 本記事では、アンコンシャス・バイアスの事例や対処法をご紹介します。 アンコンシャス・バイア... -

バンドワゴン効果とは何か?4つの心理と活用例を解説
バンドワゴン効果とは バンドワゴン効果とは、大勢の人が選択した意見と同じものを自分自身もつい選択してしまうという心理効果のことです。例えば、ランキング形式で掲載されたリストの中で一番評価の高いお店を選んでしまうといったように、バンドワゴン... -

選好の逆転とは何か?起こる要因や活用事例を解説
選好の逆転とは 選考の逆転とは、状況によって、人の好みや優先順位が変わってしまう現象です。この現象は、認知心理学者のポール・スロヴィッチとサラ・リヒテンシュタインによる、カジノでの実験で明らかにされました。 A 賞金は低いがもらえる確率は高... -
![[画像:ヒストグラム]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==)
大数の法則とは何か?その具体例と、少数の法則との違いを解説
大数の法則とは 大数(たいすう)の法則(Law of Large Numbers)とは、サンプルサイズが大きければ大きいほどその平均は母集団全体の平均に近づくという確率論です。厳密には、大数の法則は「大数の弱法則(Weak Law of Large Numbers)」と「大数の強法則(... -

カクテルパーティ効果とは何か?カラーバス効果との違いも含めて解説
カクテルパーティ効果とは カクテルパーティ効果(Cocktail-Party Effect)とは、カクテルパーティのような人が多くて周りが騒がしい環境でも、自分に関する話や必要とする情報は聞こえるという心理効果です。1953年にイギリスの心理学者のエドワード・コ... -

共有地の悲劇とは何か?起こるメカニズムと対策を解説
共有地の悲劇とは 共有地の悲劇とは個人的な利益を優先することで、過剰に利用してしまい、共有の資源が損なわれ、資源の破壊や枯渇が引き起こされることを意味します。 この概念は、1968年にアメリカの生態学者であるギャレット・ハーディンが提唱したも... -

フレーミング効果とは何か?表現によって選択が変わる認知バイアスを解説
フレーミング効果とは ダニエル・カーネマン(画像はWikipediaより) フレーミング効果(Framing effect)とは、選択肢が肯定的または否定的な意味合いで提示されているかどうかにもとづいて、人々が選択肢を決定するという認知バイアスのことです。言い換... -

コントロール幻想(人間の迷信的行動)とは何か?迷信に騙される人の心理
コントロール幻想とは ジェンキンスとウォードの研究から コントロール幻想とは、心理学用語で、「自分でコントロールできないことを、自分の行いで影響を与えられると錯覚してしまう」現象です。この現象は「人間の迷信的行動」と呼ばれることもあります... -

ダニング=クルーガー効果とは何か?できない人ほどできた気になる現象を解説
動画でも解説しています 今回のダニング=クルーガー効果については、動画でも解説していますので、ぜひご覧ください。 ダニング=クルーガー効果とは ダニング=クルーガー効果とは、心理学者のデイビット・ダニング(David Dunning)とジャスティン・クル...


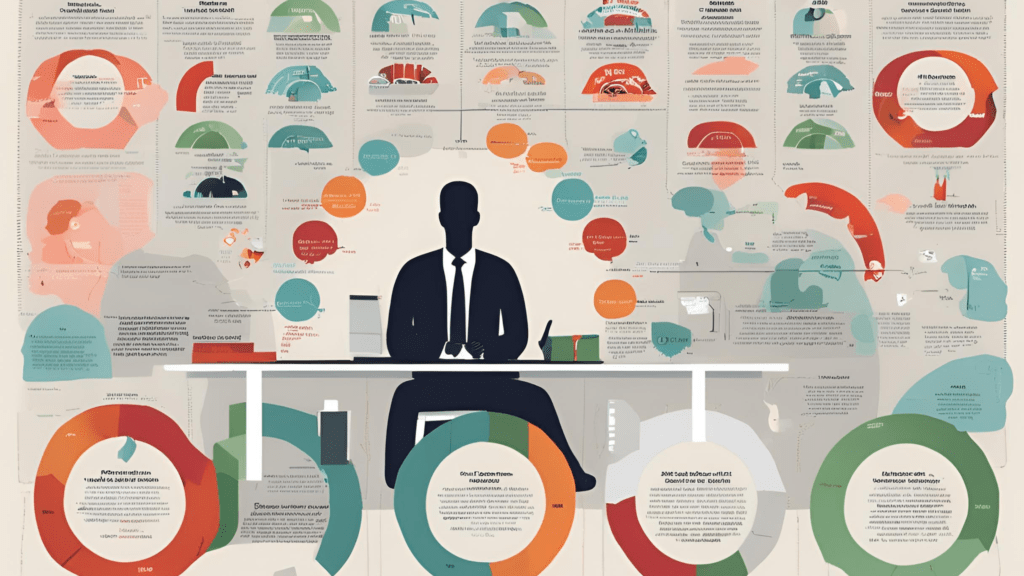
![[画像:ヒストグラム]](https://ssaits.jp/promapedia/wp-content/uploads/2025/04/web_statistics-2-1024x576.png)
