認知心理学– tag –
-

自我消耗とは?「意志力」は使うと減るバッテリーである。回復と節約の方法を解説
「朝はやる気に満ちていたのに、夕方になると仕事が手につかない…」 「ダイエット中なのに、夜になるとついお菓子を食べてしまう…」 もしあなたがこんな経験をしているなら、それはあなたの性格がだらしないからではありません。脳のエネルギーである「意... -

利用可能性バイアス(availability bias)とは何か?判断を誤らせる認知バイアスを解説
利用可能性バイアスの概要 利用可能性バイアス(availability bias)は、認知心理学や行動経済学の分野で研究される心理学的なバイアスの一つです。このバイアスは、人々が判断や意思決定をする際に、手元に容易に思い浮かぶ情報や出来事を過大評価し、そ... -

比率バイアスとは何か?数字の判断を誤らせるバイアスを解説
比率バイアスの概要 比率バイアス(ratio bias)は、統計的な判断や意思決定において、比率や割合を正確に評価することが難しい傾向を指します。人々はしばしば比率を誤解し、その結果、誤った判断を下すことがあります。比率バイアスは、統計思考や意思決... -
![[画像:代表性バイアスの例]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==)
代表性バイアスとは何か?例とともに判断を誤る原因となる認知バイアスを解説
代表性バイアスの概要 代表性バイアス(representativeness bias)は、認知バイアスの一種で、人々が情報やデータを評価する際に特定の特徴やパターンが他の要因よりも強調される傾向を指します。このバイアスは、情報を簡略化し、判断を迅速に下すために... -

二重プロセス理論とは何か?二重システム理論、二過程論とも呼ばれる意思決定プロセスを解説
二重プロセス理論の概要 二重プロセス理論(Dual-Process Theory)は、心理学や神経科学、認知科学などの分野で使用される重要な概念の一つです。二重システム理論(Dual-System Theory)や二過程論とも呼ばれるこの理論は、人間の思考や意思決定プロセス... -

スキーマの呪縛とは何か?認知負荷を下げるスキーマのメリットとデメリットを解説
スキーマの呪縛の概要 スキーマの呪縛は、認知心理学や認知科学の文脈で使われる用語で、スキーマ(認知スキーマ、認知フレームワーク)が思考や判断に対して過度に制約をもたらす現象を指します。具体的には、個人が特定のスキーマに囚われ、新しい情報や... -

非注意性盲目と見えないゴリラの実験とは何か?
非注意性盲目とは 非注意性盲目(Inattentional Blindness)とは、人間が特定の課題や刺激に集中することで、その他の周囲の情報や刺激を認識できなくなる現象を指します。言い換えれば、人間は意識的に注意を向けていることに焦点を当て、他の情報を見落... -

プライミング効果とは何か?フロリダ効果についても解説
プライミング効果とは プライミング効果とは、ある単語や観念などに接すると、その関連語が想起されやすくなるという現象のことです。 たとえば「に」と何かのひらがなを組み合わせて言葉を完成させるゲームをすると、あらかじめ食べ物の写真を見ていた人...
1

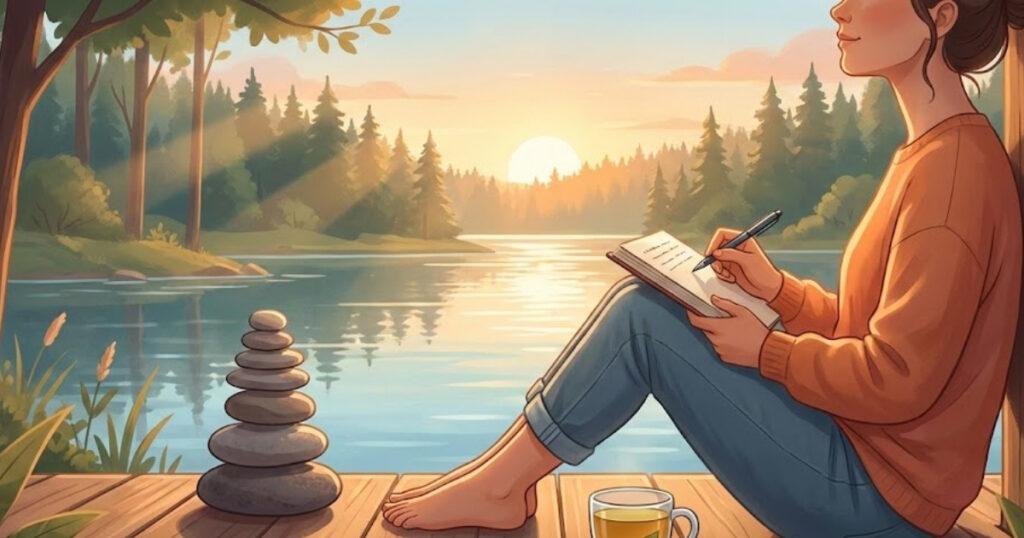

![[画像:代表性バイアスの例]](https://ssaits.jp/promapedia/wp-content/uploads/2023/10/representativeness-bias-1024x576.png)

