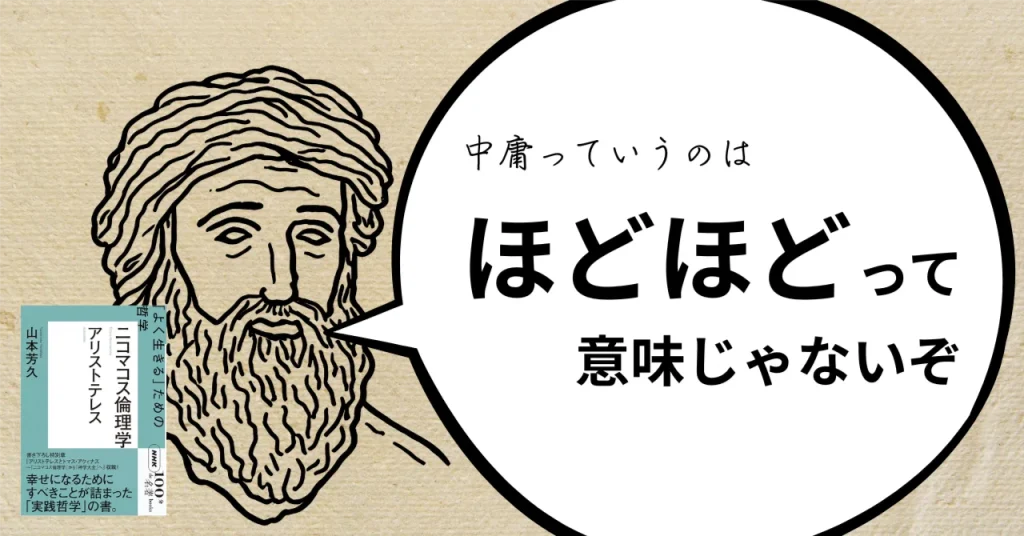【応用情報・診断士 対策】「本当のコスト」を見抜く!活動基準原価計算 (ABC) とは?
「この製品、本当に儲かってる?」
「ITシステムを導入したいけど、どれだけコスト削減効果があるか正確に知りたい」
こうした経営の根幹に関わる問いに、より正確な答えを出すための強力な管理会計の手法が、活動基準原価計算(Activity-Based Costing: ABC)です。
なぜABCが必要なの? 従来の原価計算の問題点
従来の原価計算の問題
なぜABCが必要なのでしょうか?ここからは、高級料亭の料理を例に解説していきます。
あなたは高級料亭の経営者です。
メニューには、作るのに非常に手間がかかる「特製懐石弁当」と、効率よく大量に作れる「日替わりランチ」があります。
どちらのメニューにも、調理場の光熱費や家賃、調理器具の費用など、共通の経費(=間接費)がかかっています。
従来の原価計算では、この間接費を、「売上高」や「生産個数」といったざっくりした基準で、両方のメニューに割り振っていました。
たとえば、光熱費や家賃などの月々の間接費が100万円だったとします。特製懐石弁当も日替わりランチもそれぞれ月50食、あわせて100食分つくられていたとします。
そうすると、特製懐石弁当も、日替わりランチも、1食あたり1万円の間接費が掛かっていると考えるのが従来の原価計算です。

従来の原価計算は単純明快で、間接費の計算がしやすいのが特徴です。しかし、この方法では、「日替わりランチ」も「懐石弁当」も同じ1食(生産個数)として扱われると、手間が全く違うのに、同じだけの間接費が乗せられてしまいます。
その結果、「懐石弁当」のコストは安く見えすぎ、「日替わりランチ」のコストは高く見えすぎる、というコストの歪みが発生します。これでは、懐石弁当が「実は赤字」であることを見逃してしまうかもしれません。
ABCの基本的な考え方:「活動」に着目する
ABCは「手間が全く違うのに、同じだけの間接費が乗せられてしまう」という問題を解決します。
基本的な考え方は「コストは、活動(Activity)によって発生する」というものです。
間接費を「調理」という一つの塊で捉えるのではなく、以下のような具体的な活動(アクティビティ)に分解します。
- 「食材の下ごしらえ」活動
- 「複雑な盛り付け」活動
- 「食器の洗浄」活動
- 「新メニューの考案」活動
そして、それぞれの活動に「どれだけコスト(人件費など)がかかっているか」を集計します。
最後に、「懐石弁当」は「複雑な盛り付け活動」を何分使ったか?「日替わりランチ」は何分使ったか? という活動の消費量(=コスト・ドライバー)に応じて、コストを正確に割り振ります。
これにより、「手間のかかる製品には、その手間(活動)にかかった分だけ、きっちりコストを負担させる」ことができ、製品ごとのより正確なコストがわかるようになるのです。
過去問に挑戦!
令和7年度 応用情報技術者試験 春期 午前 問64より
製品 X と製品 Y を販売している企業が、見積作成と提案書作成に掛かる業務時間を、それぞれ 20% 削減できるシステムの構築を検討している。Activity-Based Costing を用いて、次の条件が洗い出された。本システム構築による製品 X の見積作成と製品 X の提案書作成に関する月間総人件費削減効果は幾らか。
[条件]
- 製品 X の見積作成に掛かる月間業務時間は、50 時間
- 製品 X の提案書作成に掛かる月間業務時間は、50 時間
- 製品 Y の見積作成に掛かる月間業務時間は、100 時間
- 製品 Y の提案書作成に掛かる月間業務時間は、400 時間
- 製品 X と製品 Y の見積作成に掛かる月間総人件費は、60 万円
- 製品 X と製品 Y の提案書作成に掛かる月間総人件費は、360 万円
- 見積作成と提案書作成は、それぞれ人件費単価が異なる部門が担っている。
- 製品 X と製品 Y の見積作成に掛かる人件費単価は、同じである。
- 製品 X と製品 Y の提案書作成に掛かる人件費単価は、同じである。
ア 4 万円
イ 8 万円
ウ 12 万円
エ 14 万円
解答と解説
この問題は、システム導入の効果測定という、まさにABCが得得意とする分野の問題です。
ステップ1: 「活動」ごとのコスト単価を計算する
まず、従来の「ざっくり」計算ではなく、ABCの考え方で「活動ごと」の1時間あたりの人件費単価を計算します。
この問題における「活動」は、「見積作成」と「提案書作成」の2つです。
①「見積作成」活動の単価(円/時間)
- 条件から、この活動にかかる総コストと総時間を探します。
- 総コスト(月間総人件費): 60万円
- 総時間: 製品X (50時間) + 製品Y (100時間) = 150時間
- 見積作成の単価: 60万円 ÷ 150時間 = 4,000円/時間
②「提案書作成」活動の単価(円/時間)
- 同様に、この活動にかかる総コストと総時間を探します。
- 総コスト(月間総人件費): 360万円
- 総時間: 製品X (50時間) + 製品Y (400時間) = 450時間
- 提案書作成の単価: 360万円 ÷ 450時間 = 8,000円/時間
ステップ2: システム導入対象(製品X)の活動コストを計算する
次に、今回のシステム導入で削減対象となる「製品X」が、それぞれの活動で月間いくらコストを使っているかを計算します。
① 製品Xの「見積作成」コスト
- 活動時間: 50時間
- 活動単価: 4,000円/時間
- コスト: 50時間 × 4,000円/時間 = 200,000円 (20万円)
② 製品Xの「提案書作成」コスト
- 活動時間: 50時間
- 活動単価: 8,000円/時間
- コスト: 50時間 × 8,000円/時間 = 400,000円 (40万円)
ステップ3: 削減効果(金額)を計算する
最後に、システム導入による削減効果を計算します。
- 削減対象のコスト合計(製品Xの関連コスト):
20万円 (見積) + 40万円 (提案書) = 60万円 - 削減率: 業務時間を20%削減できる
(=人件費も20%削減できる) - 月間総人件費削減効果: 60万円 × 20% = 12万円
したがって、正解は ウ (12万円) となります。
まとめ
ABCは、単なる原価計算の手法ではなく、「どの活動にどれだけ経営資源が使われているか」を可視化するマネジメントツールです。
応用情報技術者試験では「IT導入の効果測定」として、中小企業診断士試験では「より正確な原価計算」や「BPR(業務プロセス改善)の分析」として、非常に重要な概念となりますので、ぜひマスターしておきましょう!