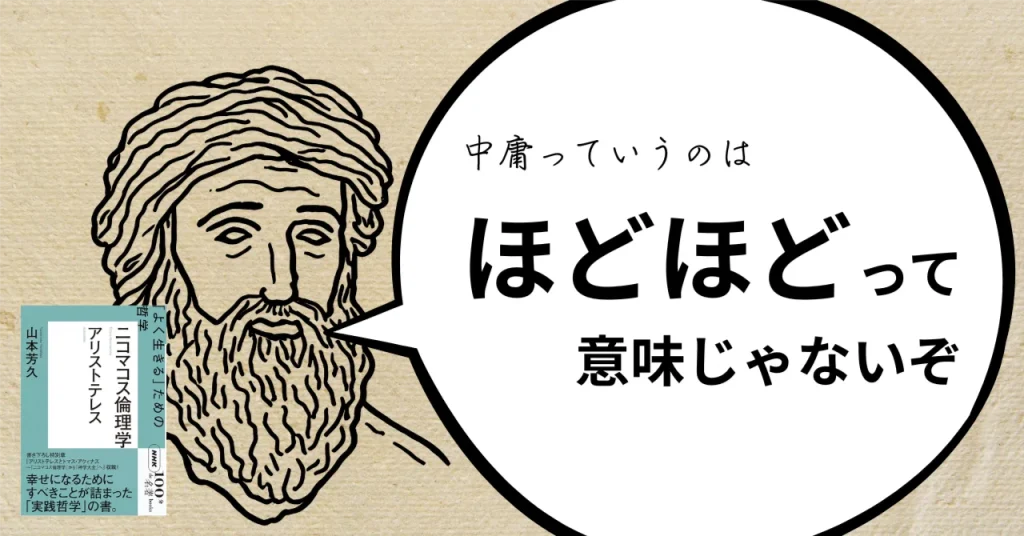【応用情報・診断士 対策】松竹梅で決まり!「プライスライニング戦略」と価格戦略4選
商品の「価格」をどう決めるか。これはビジネスの成否を分ける重要な要素です。
応用情報技術者試験や中小企業診断士試験では、様々な「価格設定(プライシング)戦略」が問われます。
今回は、応用情報技術者試験の過去問(令和7年春期 午前問68)を題材に、代表的な4つの価格戦略を整理しましょう。
【問題】
プライスライニング戦略はどれか。ア 消費者が選択しやすいように,複数の価格帯に分けて商品を用意する。
イ 商品の品質の良さやステータスを訴えるために意図的に価格を高く設定する。
ウ 商品本体の価格を安く設定し,関連消耗品の販売で利益を得る。
エ 新商品に高い価格を設定して早い段階で利益を回収する。
正解は「ア」:プライスライニング戦略 (段階価格)
正解は ア です。
プライスライニング戦略(段階価格政策)とは、商品をバラバラの価格で売るのではなく、「松・竹・梅」のようにいくつかの価格帯(ライン)にグループ分けして販売する手法です。
- 例: スーツ量販店(19,000円、29,000円、39,000円の3プライス)
- メリット:
- 消費者: 予算に合わせて選びやすくなる(選択の負担が減る)。
- 販売者: 在庫管理が楽になり、真ん中の価格帯(竹)に誘導しやすくなる(極端の回避性)。
他の選択肢は何の戦略?
不正解の選択肢も、すべて名前のついた立派な戦略です。試験によく出るので、あわせて覚えてしまいましょう。
イ:名声価格戦略 (Prestige Pricing)
名声価格戦略とは、商品の品質の良さやステータスを訴えるために、意図的に価格を高く設定する戦略です。「威光価格」や「プレミアム価格」などとも呼ばれます。
この名声価格戦略のポイントは「価格が高い=品質が良い」という消費者の心理を利用していることです。あえて値下げをせず、ブランドイメージを守ります。
- 例: 高級ブランドバッグ、高級腕時計、高級車
ウ:キャプティブ価格戦略 (Captive Pricing)
キャプティブ価格戦略とは、商品本体の価格を安く設定し、関連消耗品の販売で利益を得る戦略です。
つまり、主製品(本体)を安く売って顧客を捕まえ(Captive=捕虜)、それを使うために不可欠な消耗品や付属品を高く売ることで、トータルで利益を上げます。
- 例:
- プリンターとインク: 本体は安いが、インクが高い。
- カミソリ: 柄(ホルダー)は安く配り、替刃が高い。
エ:スキミング価格戦略 (Skimming Pricing)
スキミング価格戦略とは、新商品に高い価格を設定して早い段階で利益を回収する戦略です。
製品の導入期に、高くても買ってくれる層(イノベーターなど)をターゲットに高価格を設定し、開発費などの投下資本を早期に回収する戦略です。市場の「上澄み(Skim)」をすくい取るイメージです。
- 例:
- 最新のiPhone、発売直後のゲーム機
対となる「ペネトレーション価格(浸透価格)戦略」
スキミング価格戦略とは、まったく逆の発想である「ペネトレーション価格(浸透価格)戦略」も、資格試験には頻出の用語です。
ペネトレーション価格戦略は、最初から安い価格を設定し、一気に市場シェアを獲得する戦略です。
まとめ
| 選択肢 | 戦略名 | キーワード | 例 |
|---|---|---|---|
| ア (正解) | プライスライニング | 段階、松竹梅、選びやすい | スーツ、コース料理 |
| イ | 名声価格 | ステータス、あえて高く | 高級ブランド |
| ウ | キャプティブ価格 | 本体安く消耗品高く、捕虜 | プリンターとインク |
| エ | スキミング価格 | 早期回収、上澄み | 最新ガジェット |
マーケティングの価格戦略は、ITコンサルタントとしても、クライアントのビジネスモデルを理解する上で非常に役立つ知識です。ぜひセットで覚えておきましょう!