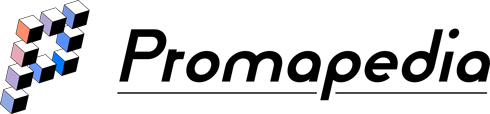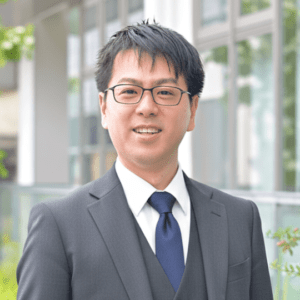因果推論の成り立ち
2021年に因果推論を用いた効果測定がノーベル経済学賞を受賞したことで、因果推論への注目度が高まっています。
しかし、因果推論は近代に至るまでは科学的な学問で取り扱うことのないタブーとされてきました。
因果とは人間にとって身近なもので、「朝が来たから鶏が鳴く」のような関係性を指します。
ところが、数式の中で「朝が来たから鶏が鳴いた。鶏が鳴いたから朝が来たわけではない」と表現することは困難です。
近代統計学において因果推論は非科学的で「パーティーの話題としては良いが、科学の対象とは言えない」と言われていました。
統計学がたどってきた因果との歴史と、これから因果推論を理解するために必要な「因果のはしご」について解説します。
統計学のはじまり -平均への回帰-
フランシス・ゴルトン(Francis Galton、1822-1911)は、進化論で知られるダーウィンの従兄弟であり統計学者、遺伝学者です。
ゴルトンは、自身の家系に傑出した科学者が多くいたことから、人間の能力と遺伝の関係に強い関心を持っていました。
そこで、イギリス人の中から「特に優れている」と考えた600人以上を集めて血統を遡り、遺伝子と優秀さの関係性を探る研究を行いました。
結果は、「優れている人物の息子や父親は本人ほどには優れていない」というものでした。
この研究の結論を受けて、ゴルトンは「因果は非科学的なものである」と定義します。
また、ゴルトンはこの親子関係の研究を進めるうちに「平均への回帰」を発見します。
平均への回帰とは、データの偏りがあったとしてもいずれ平均値付近に収束するという考え方です。
- 身長の低い親から生まれる子供は、親より若干身長が高い
- 身長の高い親から生まれる子供は、親より若干身長が低い
このように、親の身長のデータに偏りがあったとしても、子供に受け継がれていくにつれて次第に平均的になっていきます。
平均への回帰により「優秀な人の子供が本人ほどには優れていない」ことも説明できると結論づけました。
この「平均の回帰」は現在の統計学においても頻繁に使われる考え方で、薬の効果などについて「数値の改善は薬の影響ではなく平均への回帰によるもの」といった結論が付けられることがあります。
また、ゴルトンは「平均への回帰」を求める過程で「相関係数」の考え方も発見しています。
因果の封印 -相関係数の確立-
カール・ピアソン(Karl Pearson、1857-1936)はゴルトンの弟子でありイギリスの数学者、統計学者です。
ピアソンは数学に長けており、ゴルトンが提唱した相関関係の数式を確立しました。
そのため、現在の統計学において相関係数という言葉を使うときは「ピアソンの積率相関係数」を指しています。
ピアソンは絶対的な因果を否定しており、因果関係に見えるものは「時間的な前後を持つ相関関係である」としています。
繰り返し起きる相関関係のある事象が、人間の感情による非科学的な意味づけで因果であるかのように見えているだけであり、それらは科学の対象ではないと考えました。
ピアソンは現代の統計学の基礎である検定や主成分分析などを完成させ、現代統計学において大きく貢献した人物です。
その権威あるピアソンが因果の存在を非科学的なものと位置付けたことで、その後の統計学の中で因果関係について言及することがタブーとされました。
因果革命 -パス解析、強いAI-
シューアル・ライト(Sewall Wright、 1889-1988)は、モルモットの毛の色を決める要因について、遺伝要因と後天的要因、それぞれの親から受ける影響の強さを図示し、その因果性について言及しました。
この時作られた図は「パス解析」と呼ばれ、現代の統計手法でも用いられています。
しかしパス解析の考え方は当時のピアソンの思想が強い統計学において受け入れられず、研究結果は思い込みや非科学的であるとして痛烈な非難を浴びました。
のちに強いAIと呼ばれる汎用AIの実現を目指すにあたり、意思決定や因果というテーマの重要性が増してきたことで再度注目されています。
「因果のはしご」とは
因果のはしごとは、因果関係を理解するための「関連づけ」→「介入」→「反事実」という3つの認知段階です。
ジューディア・パール(Judea Pearl、1936-)によると、人間は3段階目の「反事実」まで理解することができるものの、AIやロボットは1段階目の「関連づけ」までしかできません。
急速なAIの発展で強いAIの実現がそう遠くないと考える人も多くいますが、パールは因果のはしごをのぼる強いAIの実現はまだ先であるとしています。
因果のはしご1段目:関連づけ
関連づけの認知段階では、データや状況を観察することができます。
変数がお互いにどう関連しているかを考えたり、Xという事象でYはどのように変化するかを見極めて判断を行います。
たとえば、AIによる病気の推定などが該当し、「頭痛の症状がある時どのような病気か?」を判断することができる認知段階です。
因果のはしご2段目:介入
介入の認知段階では、データに干渉したり、自ら行動を起こすことで状況に影響を及ぼすことができます。
Xを行うとYは期待する状態になるか?といった形で考察しながら行動します。
たとえば、「この薬を飲むと頭痛が治るのか?」や「タバコをやめたらどうなるか?」といったことが考えられるようになります。
パールは、このような認知段階は類人猿のような発達した脳を持つ動物に可能であるとしています。
因果のはしご3段目:反事実
反事実の認知段階では、過去を振り返り物事を理解、想像することができます。
もしこうしていたらあのときどうなっていたのか?と過去に起きなかった選択肢から今を想定して理解を深めます。
また、Xが原因でYが起きたのか?といった因果の結びつきを考えることも可能です。
たとえば、「頭痛が治ったのは薬のおかげか?平均への回帰か?」
といった形で因果と反事実を考察することができる認知段階です。
これらは現状人間のみが持っている能力であり、AIやロボットが反事実まで認知段階を上げるのはまだ遠い未来であると考えられます。
参考
書籍
- Judea Pearl他(著)、夏目大(訳)『因果推論の科学 「なぜ?」の問いにどう答えるか』文藝春秋
Webページ
- https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/173207/1/ronso_38_061.pdf(2023年5月23日確認)
- https://www.tufu.or.jp/horizon/2021/2310(2023年5月23日確認)
- https://navymule9.sakura.ne.jp/Karl_Pearson.html(2023年5月23日確認)