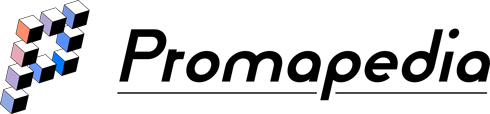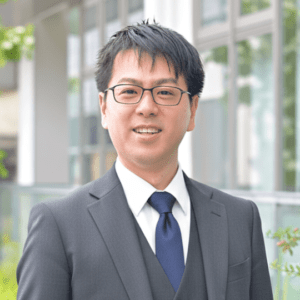はじめに
今回は南満州鉄道株式会社(以下「満鉄」と略記)の初期の経営戦略を、大戦略・戦略・作戦戦略・戦術の4つのレベルに注目してまとめていきます。
満鉄は本来の鉄道業務に加え、鉄道付属地の開発、ホテルの経営、大連での貿易業務などを行い、多角化を深めていった企業でした。
こうした経営方針には、初代総裁・後藤新平の意思が少なからず影響を与えていました。
一方で、満鉄総裁全17代の平均在任期間が26.4ヶ月であった中で 、後藤の1年8ヶ月という在任期間は短いものでした。
この短期間に後藤はどのような経営戦略をたてたのでしょうか。今回は後藤が作成した満鉄経営の青写真を分析していきます。
大戦略 -三大臣命令書-
日露戦争の戦利品
1905年、日露戦争の講和条約がポーツマスで結ばれると、日本はロシアが経営していた長春以南の東清鉄道南部線の経営権を獲得しました。
1906年1月7日には西園寺内閣の下で「満州経営委員会」が発足し、満州経営の具体的な計画が講じられ始めました。同年5月22日に西園寺は首相官邸で「満州問題に関する協議会」を開き、その2週間後の6月7日には「満州鉄道株式会社設立ノ件」が公布されました。8月1日には後藤が総裁就任を正式に承諾し、満鉄創立の地盤が固められます。そして1907年4月1日より満鉄は営業を開始しました。
満州の東インド会社
満鉄は鉄道業務と並行してその付属地の開発を行い、東インド会社のように企業の体を持って満州を統治することが目的とされていました。
付属地の開発の具体的な内容に関しては、満鉄の事業目的を逓信・大蔵・外務の三大臣が作成し、後藤が総裁就任を承諾した8月1日に公布された「三大臣命令書」とよばれる条文から読み取ることができます。
全26条から成る三大臣命令書では、鉄道の経営とともに第4条で付帯事業について言及がなされています。付帯事業としては撫順炭の採掘を主とする鉱業、水運業、電気業、鉄道貨物の委託販売業、倉庫業、鉄道付属地における土地および家屋の経営、その他政府から許可を受けた事業の営業が想定されていました 。
このように、満鉄の経営は創立当初から多角化が想定・推奨されていました。では、総裁に就任した後藤はどのようにして、この満鉄の課題を消化しようとしたのでしょうか。次は後藤の動きを見ていきましょう。
戦略 -文装的武備-
後藤の構想
上記の三大臣命令書が公布される前から、後藤は満州経営について独自の構想を練っていました。
満鉄総裁就任前、後藤は台湾総督府民政長官の任についていました。ポーツマス条約終結前日である1905年9月5日、後藤は台湾総督であった児玉源太郎を奉天の満州軍総司令部に訪ねます。この時、後藤は満州の視察を行い、その考えは「満州経営策梗概」としてまとめられました。
その冒頭で後藤は「戦後満州経営唯一の要訣は、陽に鉄道経営の仮面を装い、影に百般の施設を実行するにあり」と述べ、三大臣命令書と同じように、付属地の開発や工業の奨励などにより満州を実質的に統治するという構想を練っていました。
満鉄総裁就任が決定すると、後藤はその経営にあたって「文装的武備」という言葉を掲げました。その意味を後藤は「文事的施設を以て他の侵略に備え、一旦緩急あれば武断的行動を助くるの便を併せて講じ置く事」、「王道の旗を以て覇術を行ふ」ことと述べています 。後藤は「文装的武備」という言葉を以て、満州経営という国家意思と企業としての満鉄を結びつけ、満鉄を介して満州を統治するという大戦略を遂行しようとしていたと言えましょう。
再度日露間の衝突があると考えていた後藤は、鉄道網の拡大によって武断的行動、即ち実際の戦闘の後援をしようとしました。
他方、「文事的施設を以て他の侵略に備え」るという点に関しては、ホテル事業がよくその意味を体現しているでしょう。
ポーツマス条約終結直後、米国の鉄道王・ハリマンによる買収問題で紛糾した満鉄は、満鉄経営を円滑に行うために、外国からの干渉を防がなければなりません。そのためには、対外に満鉄経営が好調であり、日本人の独力で経営が可能であることを積極的に示す必要があります。
後藤は満鉄に赴任すると、各地にホテルを建造し、欧米人を誘致しました。後藤はホテル業を介して、欧米に満鉄をアピールするとともに、満州が日本人による排他的精神によって開発されているのではなく、全世界の福祉増進につながるように満鉄が同地を開発していることを訴えました 。
作戦戦略 -「調査」を中心とする戦略-
1907年4月1日から営業を開始した満鉄本社には5つの部署が設けられました。総務部、運輸部、鉱業部、地方部、そして調査部でした。開業当初の調査部では清国の法制度や慣習の調査を行い、付属地の開発を行う中で清国と法制度上の衝突が起こらないように備えました 。
満鉄本社の調査部は1908年12月には調査課となり、規模を縮小させます。しかし、1908年11月には東京支店に東亜経済調査局が設置されており、満鉄全体としての調査能力が低下したとは言えないでしょう。同局は本邦初の組織的な経済調査機関として設立され、満鉄の業務の範囲に留まらず、グローバルなインフォメーション収集機関として、広く世界経済の調査・研究を行いました 。
さらに満鉄は調査期間の他にも、中央試験所・地質試験所などの研究機関も擁していました。
中央試験所は後藤の提唱により1907年10月に設立され、翌年7月に業務を開始します。当初は関東都督府に所属していた中央試験所は1910年に満鉄に移管されました。その後、同所は撫順の石炭や蒙古の天然ソーダなどの満州の資源に関する調査を行いました。
地質調査所は満鉄工業部地質課を起源とします。地質課は1908年に鉱業課となった後、1910年に本社直属の地質研究所に改組され、1919年に地質調査所となりました。地質調査所という名称になる以前から、その前身の課は精力的に満州各地を踏査し、鉱山の調査を行っています。こうした調査・研究機関は満鉄の多角化のコストを抑え、業務の拡大を下支えしたと言えましょう。
戦術 -「午前八時主義」の人事-
実際に満鉄の業務を担ったのはどのような人物だったのでしょうか。この点に関しては、後藤の「午前八時主義」が有名です。
時間は年齢を意味しており、目覚めたばかりの若い人材を用いるというのが「午前八時主義」の意味です。満鉄の創立当初、トップであった後藤は50歳、副総裁の中村是公は40歳と若く、三井物産から営業担当の理事に抜擢された最年少の犬塚信太郎は32歳でした。
『後藤新平伝』では、このように若年の人材を抜擢した理由を、後藤の「名高の骨高はだめだ」という口癖と併せて、「声名を天下に買って、既にその全盛期を過ぎたる人物は、実際の役に立たぬ人間多しとの意味である 」と述べています。しかし、満鉄の経営にあっては、また違う側面も見えてきます。
まず、組織のコントロールという点で若年の人材である必要があったのではないでしょうか。試みに個人名義で満鉄株を取得している株主を見ていくと、取得株数が多い順に大倉喜八郎(91株)、古河虎之助(46株)、岩崎久弥(18株)、渋沢栄一(4株)が挙げられます 。
1907年の満鉄設立当時、大倉は70歳、古河は20歳、岩崎は42歳、渋沢栄一は67歳でありました。2代目の急逝によって1905年に後を継いだ古河は他に比して著しく若い印象があります。
一方で、大倉・渋沢は後藤よりも20歳近く年長であり、岩崎は後藤よりは年下であるものの、副総裁である中村是公よりは年上です。後藤はこうした財界の有力者に協力を仰ぐことも可能であったのでしょうが、その場合は総裁・副総裁よりも年長者になる可能性が強く、経営の方針をめぐっての軋轢が生じかねません。
また、創立当初から多角化を想定していた満鉄では、広範な業務にそれぞれ高齢・高給のスペシャリストを雇うとなると、人件費が膨張するおそれがあります。それよりも、若くて労賃が安く、仕事意欲のある人材をスペシャリスト・ゼネラリストに育て上げることが経営上効率のよい選択であったといえるでしょう。
このように、後藤の「午前八時主義」の人事は後藤の人間観を表しただけでなく、満鉄の経営を円滑に行うための方便という面もあるのではないでしょうか。
後藤のリーダーシップ(まとめにかえて)
三大臣命令書が掲げた満州経営の目的を達成するため、後藤は「文装的武備」という言葉をもって鉄道会社の経営と満州経営という政治目的を結びつけました。
この多角化戦略を成功させるカギとなったのが調査部と試験所の活用でした。そして、これらの業務を担う人材には、経営を円滑に行うために「午前八時」の若い人材を抜擢しました。こうした戦略が功を奏し、加えて後藤が作成した青写真を台湾以来の腹心・中村是公が忠実に実行に移した結果、操業開始から満鉄の営業成績は右肩上がりでした 。
最後に戦略遂行に影響したであろう後藤のリーダーシップについて考察していきましょう。満鉄における後藤の活動としては人材抜擢のエピソードが有名です。「午前八時」の人材を揃えるため、後藤は様々な方面に人を求めました。三井物産の犬塚や、京都帝国大学から調査課理事として迎えた岡松参太郎を登用する際、後藤は三井物産や文部省と衝突しました。
しかし後藤は相手先と粘り強く交渉し、人材の獲得に成功しています。その成功の秘訣を後藤は「口説き上手、使い上手といわれたのは、誠心誠意、人に対するからだ」と述べています。このように、リーダーが備えていなければならない「信頼」、「人」の力を後藤は十分に理解していたと言えましょう。
また後藤は「言葉」の使い方も巧みでした。後藤は台湾統治における「生物学的統治」、満鉄における「文装的武備」など目標を装飾する能力に長けていました。また、後藤は1907年3月29日より発行された「南満州鉄道株式会社・社報」にほぼ毎号執筆しています 。後藤は社報を介して、自身の意思を末端まで浸透させることに努めました。
このように、後藤新平は大風呂敷と呼ばれる壮大な計画をたてるだけでなく、その目的・意思を隅々に浸透させようとする姿勢が、満鉄経営を成功に導いたと言えるのではないでしょうか。
参考文献
- 小林英夫『満鉄 「知の集団」の誕生と死』吉川弘文館 、1996年
- 佐藤篁之『「満鉄」という鉄道会社』交通新聞社新書、2011年
- 鶴見祐輔『後藤新平伝』第2巻、勁草書房、1966年
- 満鉄会『満鉄四十年史』吉川弘文館、2007年
- 山田豪一『満鉄調査部 栄光と挫折の四十年』日本経済新聞社、1977年